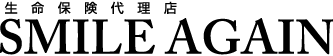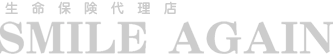人間誰しもこの世に生を授かったとしても、いつかはお亡くなりになる瞬間が必ず訪れます。
それはすぐにやって来るかもしれませんし、50年後か、あるいは100年後かもしれません。
そんなことは誰にもわからない。
今を懸命に生きている瞬間に、いつお亡くなりになるかなんて誰も考えたくない。
ただ、いつかは必ずお亡くなりになる瞬間がやって来る。
その後に残るのは死後の整理。
葬儀や供養の執り行いはもちろんのこと、死後の行政手続きに故人が残した家財や衣類を整理する遺品整理。
そして遺産の相続。
「遺産の相続?ウチ、そんなにお金になるようなモノ無いから!」
お客さまはよくそうおっしゃいますがいざ相続が発生すると、金銭の額や相続財産の価値などにかかわらず揉める時はガチガチに揉めます。
遺産分割のもつれは実際、預貯金の金額や財産の価値だけでは測れない部分。
決して億単位や何千万単位の、高額な遺産だけが引き金となって揉めるワケではありません。
金額等や遺産の価値にかかわらず、揉めるときは本当に揉めるんです。
それは私が過去に某金融機関に所属していた時代も保険代理店を続ける今も、お客さまの身近でおきているリアルな現実。
別に一人の遺族が遺産を独り占めしようとしているワケではありません。
それでもだいたいは遺産の分割割合で揉めているように見えますが、そこには必ず私的な感情が複雑に絡み合っているように思われます。
たとえば、
「私は介護が必要になった父親を見てきた!」
あるいは、
「ほかの兄弟は父親に対して何もしてこなかったのに!」
みたいな。
そんな状況だったら心情的には、これまで献身的に父親の介護をおこなってきたことへの”寄与分(父親に対しての貢献度)”も主張したくなるでしょう。
その気持ちがほかの遺族にも伝われば、何の問題もないでしょうが・・・・・。
ただほかの遺族にも「法定相続分(民法で定める遺産分割の目安)」の遺産分割を主張する権利はあります。
父親の介護をおこなってきた寄与分を考慮したとしても、遺族間でみな同じ考えに落ち着くとは限りません。
遺族間での話し合いによる遺産分割がまとまらなければ、家庭裁判所で調停委員会(裁判官1名調停委員2名以上)が間に入り「遺産分割調停」をおこなうことにもなるでしょう。
「遺産分割調停」は調停委員会が間に入るとしても、原則、遺族間での話し合いの場になりますので、お互いが権利を主張し合えばここでも意見が平行線をたどることも十分考えられます。
「遺産分割調停」でも話がまとまらなければ、もう裁判所で遺産の割り振りを決めていただく「遺産分割審判」です。
そうなれば納得のいく遺産分割となるはずがありません。
もともと主張は平行線ですから。
ここまでかなりの時間とお金を費やしても最終的にはどちらかが妥協する形となり、わだかまりだけを残してやがて遺族間の信頼関係も薄れていくことでしょう。
故人が残した財産が残された遺族間の絆までも壊していく。
本当はそんな事、誰も望んでいないのに。
そうならないためにもお元気なうちに、相続についてはしっかり考える必要があります。
それが残された遺族への”最後の思い”につながりますので。