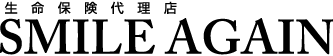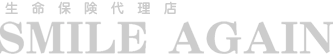現代は”人生100年時代”とよく言われますが人間の構造上、年齢を重ねていけばどうしても肉体は弱っていきます。
若いころは簡単にできた事が、年を取ってから時間がかかるようになった!(できなくなった!)
”家の中のちょっとした段差も踏み越えることが困難”
”少しの距離を歩くにも時間がかかる”
”浴槽が跨げない”
それは年齢を重ねていけばいくほど痛感させられる現実の世界。
そしていつかは日常生活を一人で送ることが難しくなり、日々ほかの人の手を借りないといけない時がやってくるかもしれません。
もしそうなったら?
冒頭でもお伝えしましたが高齢になればなるほど肉体は衰え、日常生活ではほかの人の手を借りる場面がだんだん増えてくるでしょう。
そして自立した生活が困難になってきた時のために介護保険サービスが存在します。
具体的には65歳以上の方(第1号被保険者)や40歳から64歳(第2号被保険者)までの特定の病気を患っている人が対象です。
どうしても「介護」と聞くと高齢者のケースを思い浮かべますし、確かに要介護認定を受けられるのは原則として”65歳以上”となっています。
ただここでちょっと注目いただきたいのが、40歳から64歳までの年齢層にも要介護認定を受けている方々がいらっしゃること。
| 65歳以上 | 40~64歳 | 合計 | 割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 100.8万人 | 1.2万人 | 102万人 | 14.4% |
| 要支援2 | 97.6万人 | 2万人 | 99.6万人 | 14.1% |
| 要介護1 | 144.3万人 | 2.1万人 | 146.4万人 | 20.7% |
| 要介護2 | 116.4万人 | 2.7万人 | 119.1万人 | 16.8% |
| 要介護3 | 90.9万人 | 1.8万人 | 92.7万人 | 13.1% |
| 要介護4 | 87.8万人 | 1.6万人 | 89.5万人 | 12.6% |
| 要介護5 | 57.4万人 | 1.6万人 | 59万人 | 8.3% |
厚生労働省の資料によると、2024年(令和6年)3月末時点で要支援・要介護に認定された方の総数は708万人。
その中でも40歳から64歳の方でも要支援や要介護1・要介護2の認定だけではなく、日常生活の全てにおいて介護が必要な”要介護5”の認定を受けている方々もいらっしゃいます。
その要因は末期がんや脳血管疾患など16種類の特定疾病により要支援・要介護が認定されたケースです。
<40歳以上65歳未満の人に公的介護保険が適用される16種類の特定疾病>
●筋萎縮性側索硬化症(ALS)
●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗しょう症
●多系統萎縮症
●初老期における認知症
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
●閉塞性動脈硬化症
●関節リウマチ
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
逆に言えば40歳から64歳までの方だと要支援・要介護が必要でも、上記の特定疾病に該当しなければ公的な介護保険サービスを受けることができません。
そのうえ残念ながら40歳から64歳までの年齢層だと、”交通事故”や”ケガ”では要支援・要介護認定の対象外です。
40歳未満だと介護保険適用外になり、要支援・要介護の認定自体がありません。
ここで考えられるのが「40歳から64歳までの年齢層で特定疾病以外の病気やケガにより、どうしてもほかの人の手を借りなければ生活できない時はどうしたらいいの?」ってところ。
あるいは40歳未満の場合は?(障害福祉サービスなどもありますが)
もしかしたら40歳から64歳の方々でも要支援・要介護に認定されるのはごく一部で、本当はもっと介護保険サービスを必要としている40歳から64歳までの人たちがいるとすれば?
もちろん65歳以降に「介護」が必要になった時のための、対策を考えておくことはかなり重要なことでしょう。
ただ年齢を重ねていく過程でも、ほかの人の手を借りなければ生活が困難になる可能性も決してゼロではありません。
そう考えると生命保険の”高度障害”に”三大疾病特約”、あるいはケガの”傷害特約”などはいざという時にかなりお役に立てると思いますが。
「介護」とは、高齢や病気、障害などで日常生活が困難な人を支え、尊厳ある自立した生活ができるよう手助けすることです。
それでも現行の介護保険サービスは65歳以降に重きを置いていますので、65歳未満でもし介護が必要になった時の対処法にもしっかり目を向けておくべきでしょう。
”人生100年時代”
その言葉の裏側にはかなりのリスクが潜んでいますから!